AIは指示次第──「誰に、どう頼むか」で変わる文章
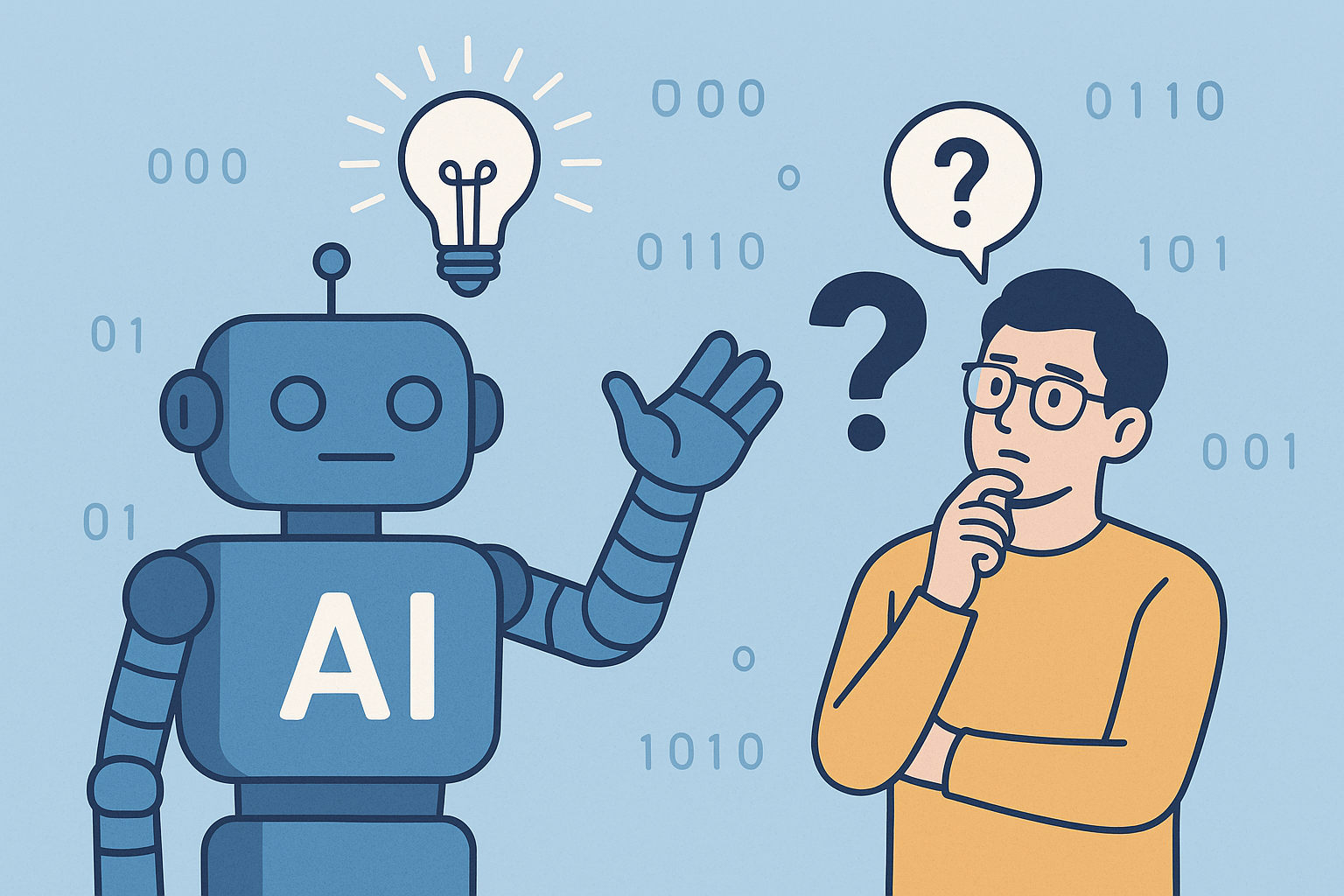
こんにちは。Uです。
前回(2024/12/15)がAIをテーマとして記載しましたので、今回もAIについて思ったことなどを書いていこうと思います。
AIはそれっぽい指示を出せばそれっぽい答えが返ってきます。
ただ、AIは万能ではなく、使い方次第で出力内容に大きな違いがあるようです。
「研究者として」や「経営者として」などの役割りはもちろんですが、知能レベルの指定も効果的であると感じています。
例えば以下の文章をベースに見ていきます。これは私がブログに何を書こうかなと適当に書いた下書きです。主張がぼけて印象に残らない文章かと思います。
これをAIによりよい文章にしてもらいます。
ベース文章:
====================
こんにちは。Uです。
10月で入社1年が経ちました。
経験も浅く、ブランクも長い中での入社でしたので、わからないことが多い中で業務に取り組む日々でした。
特に弊社は引継ぎを強みとする会社ですので、未経験の言語やフレームワークに触れることはもちろん、仕様書等が無い中でソースベースで業務ロジックを把握する必要があるなど、
知識経験が乏しい私にはソースを理解・調査の段階で四苦八苦する場面が多々あり、力不足を実感する一年でした。
周りの先輩方の助けもあり、ソースの理解や問題点の調査にも徐々に慣れてきたのではないかと思います。
2年目となりますので今後は私が周りの助けとなれるように技術の習得、伝わりやすい説明をする工夫をしていきたいと思います。
====================
まずは知能レベルと役割の指定なしでの出力を見ていきます。
入力プロンプト:
以下の文章をより訴求力、説明力のある文章に仕上げてください。{ベース文章}
出力:
====================
こんにちは、Uです。
この10月で入社から1年が経ちました。
振り返ってみると、経験が浅く長いブランクを経ての入社だったこともあり、最初の頃は何もかもが手探りの状態でした。特に弊社は「引継ぎ」を強みとする会社であり、未経験の言語やフレームワークに触れる機会も多く、仕様書がない中でソースコードから業務ロジックを読み解く必要がありました。
最初のうちは理解や調査の段階でつまずくことも多く、自分の力不足を痛感する場面が数えきれないほどありました。
それでも、周りの先輩方の丁寧なサポートのおかげで、少しずつソースの読み方や問題の切り分けにも慣れ、今では以前よりも落ち着いて対応できるようになってきたと感じています。
2年目に入った今、次は「教わる側」から「支える側」へと一歩進むことが目標です。
技術の習得を重ねるとともに、相手に伝わりやすい説明の仕方や、チーム全体の理解が深まるような工夫を意識しながら、日々成長していきたいと思います。
====================
続いて、知能レベルと役割を指定した際の出力です。
入力プロンプト:
あなたはIQ160の編集者です。以下の文章をより訴求力、説明力のある文章に仕上げてください。{ベース文章}
出力:
====================
こんにちは。Uです。
この10月で入社してちょうど1年が経ちました。
入社当初は、長いブランクを経ての再スタートということもあり、右も左も分からない状態からのスタートでした。
特に弊社は「引継ぎ」を強みとする会社であり、既存システムの理解や保守を通じて価値を提供する場面が多くあります。
そのため、未経験の言語やフレームワークに触れる機会も多く、さらに仕様書が存在しないケースでは、ソースコードを直接読み解いてロジックを把握する必要がありました。
この1年は、まさに「ソースと格闘した日々」でした。
理解できない箇所を何度も読み返し、試行錯誤を重ねる中で、知識や経験の不足を痛感することも多々ありました。
しかし、その分だけ一つひとつの課題を乗り越えた時の喜びも大きく、気づけば少しずつコードの流れや問題の原因を自力で追えるようになってきました。
周囲の先輩方の丁寧なサポートやアドバイスには、この場を借りて心から感謝しています。
これから迎える2年目は、「支えられる側」から「支える側」へと一歩踏み出す年にしたいと考えています。
技術の幅を広げるとともに、自分の学びや経験を分かりやすく伝えられるよう、説明力や共有の仕方にも磨きをかけていきたいです。
まだまだ成長の途中ではありますが、一歩ずつ確実に前へ進んでいけるよう努力していきます。
====================
さて、いかがでしょうか。個人的には知能レベルと役割を指定した際の出力のほうがよりよい内容になっているのではないかと思います。
せっかくなので出力された文章をAI自身に比較しどちらが良いか聞いてみます。知能レベル・役割指定なしを文章1、ありを文章2として入力します。
入力プロンプト:
あなたはプロの編集者です。 以下の文章1と文章2を確認しそれぞれ点数をつけてください。点数をつける際の基準は、「分かりやすさ」「伝わりやすさ」「共感」の3つとします。 点数を付けた後に最終的にどちらの文章が優れているかを挙げて、その理由を教えてください。
出力:
====================
~~~
{思ったより長かったので割愛}
~~~
総評:優れているのは 文章2
理由:
文章1は「整っていて誠実」、文章2は「生きていて伝わる」。
特に文章2は、経験と感情が自然に交わっており、読者が「状況を思い浮かべながら読める」構成になっています。
また、「ソースと格闘した日々」など印象的なフレーズがあり、読後に残る余韻が強いです。
そのため、共感と伝達力の両面で文章2が一段優れています。
====================
AI自身の評価でも知能レベル・役割ありの方が優れた文章であるようです。
このようにAIへの役割の指定や知能レベルの指定で、同じ目的で出力させてもその質に違いがでます。
以上、人へもAIへも伝え方、指示の仕方が大事だって話でした。
AIを使う際にはちょっと意識してみてはいかがでしょうか。
